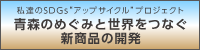私達のSDGs“アップサイクル”プロジェクトについて
――どのようなきっかけから、りんごの剪定枝を原料とした和紙や板材の開発に挑戦することになったのですか?
2011年にマーチング委員会に入会して地域の風景をイラストにし発信して地域を知ってもらおうという活動をはじめたのですが、そこから自社商品開発をして販売先を開拓して展開するなど今までにない動きができるようになりました。このイラスト名刺からの繋がりで弘前大学との協業につながり『りんごさくら和紙研究会』を発足して産学官連携で進むことが出来ました。
りんごづくりには冬から春にかけて枝の剪定作業があります。この作業でたくさんの枝が切り落とされ燃やされていてこの燃やされる素材を活かして何かに利用できないかと考えていました。

――りんごの剪定枝を原料とした和紙や板材の開発に対して、どのような思いがありましたか?
地元でできた和紙や板材を使用したお土産をつくり青森県らしさをPRできればと考えています。
というのもそうですが、今まで厄介ものとして見られる事も多かったのはりんごの剪定枝による、煙害があります。全国の皆さんが美味しい美味しいと食べていただく、全国一のりんごのはずなのに、産地ではどうして、その裏で悩まされている人がいるのか、この事実を知っているのか?
知らなかったとして、知った時にショックをうけるのではないか、そうならないためにも早急に何か活用できるものはないものか?
と出来たのが和紙でした。そしてそれは板になり、現在糸にもなって、よほど活用できるものではないかとあらためて分かりました。
りんごをただ食べるのではなく、その園地で出た『剪定枝の和紙で包まれた』、『剪定枝の箱に入った』、『剪定枝の糸からできた布でできた』、園地そのものを食べる。そんな商品であってほしいです。

――りんごの剪定枝を原料とした和紙や板材には、どのような特徴があるのですか?
・色味が自然で優しい感じがする
・りんごの木の短い繊維と楮の長い繊維がうまく混ざり、ねぷた絵や津軽凧などを描く時に染料や墨がうまくのりやすく、いい感じに滲むため使いやすい(滲みについては、サイズ剤の濃度にもよると思いますが)

――開発の苦労話や、貴社独自の工夫などありますか?
原料である剪定枝をどう効率よく収集するかには苦労しました。
対策として剪定枝や間伐材などのバイオマス発電を行っている会社と連携し、集まってくる剪定枝等廃木材の効率的な収集が出来るようになりました。
独自の工夫としては、サイズ剤の調整があります。印刷などの用途とねぷたなどの用途で適した量が違うので、用途に合わせた条件検討が必要でした。
ですが、まだまだ試行錯誤中です。

――りんご和紙を使用した商品にはどのようなものがありますか?また、りんごの剪定枝を原料とした和紙や板材に対して、地元の方やお客さま、ステークホルダーからはどのような反応があったでしょうか?
朱印帖、御祭印、組立ねぷたキット、一筆箋などがあります。
青森らしいりんごを使った和紙、未利用資源を活用した和紙なので興味深いですとか、また東京ギフトショーに出展した際には、様々な企業に興味を持ってもらい良い取組だと言って下さっております。

――SDGsや持続可能な社会の実現に対し、印刷業界はどのような課題を抱えていると思いますか?
SDGsの目標達成に貢献すると同時に資源の有効活用、廃棄物の削済、エネルギー効率の向上、そして従業員の健康と安全の確保などが挙げられます。これらの課題に対応するためには、人材育成と採用の強化も重要だと考えます。
一方で、情報を残すことに無制限にコストをかけられる組織、団体はあまりないです。最小のコストで最大の効果をあげる方法を選択しなければならないはずで、従来の単に記録媒体の期待寿命の問題等にとどまるような印刷業の捉え方だけではない新たな考えを取り入れて変化していかなければならないと考えます(口伝や周知、啓もうという視点)。

――りんご和紙、りんご板材の取り組みを振り返り、SDGsや持続可能な社会の実現に対してどのような貢献があったと感じていますか?
棄てられたり燃やされる未利用資源を活用して商品ができるという大きな自信に繋がります。この活動をきっかけに紙糸をつくるプロジェクトがはじまり、衣類をつくるとこまで発展し、未利用資源の活用が広がっています。

――印刷業界におけるSDGsや持続可能な社会の実現への取り組みは、どのように推進されるべきでしょうか?また、地元との協業についても、どのように推進されるべきでしょうか。
SDGsへの理解を経営者、社員さんが意識を高めていくことが必要だと考えます。また地元との協業は地域の困りごとを知るところから初めることが重要ではないかと考えます。
そして過去、大量消費-大量生産を是としてしまったような従来の考え方(低単価だけに目を向ける等の仕組化されることに固着した考え方)から少量多品種をこえたビヨンド少量多品種を推進し、考え方の最新流行を作り出すことが求められています。
それが新コンセプト『多品種-超微量』です

――SDGsや持続可能な社会の実現への取り組みは、本業にどのような貢献があるでしょうか?
企業姿勢としてSDGsへの取り込みは必須となると考えています。
現在は本業に大きな貢献といえるものは少ないですが必ず重要になる部分だと確信しています。

――地元との協業、SDGsや持続可能な社会の実現への取り組みについて、今後の展望をお聞かせ下さい。
価格の低さだけでなく、付加価値をつけたものが認められる世界に変化してSDGsの評価があがれば嬉しいですし、そのスモールゴール、マイルストーンとしてまず多品種-超微量の概念の浸透、実践があります。地元でも同じような考え方を持った人たちと交流して新しい価値を産み出し地域が活性化するような流れを作りたいです。

プロジェクト実績
南部町 様
不要になったアクリルパーテーションをキーホルダーに
南部町では、新型コロナウイルス対策として使っていたアクリルパーティションを再利用し、キーホルダーに作り変えるプロジェクトを行いました。
このプロジェクトは町の名所やPRキャラクターなどをデザインした6種類のキーホルダーを製作し、町内のイベントなどで来場者に配布することで、町のPRに活用しています。
この取り組みは町の若手職員で構成される「人口減少対策プロジェクトチーム」が企画しました。アクリルパーティションが不要になった際に、そのまま廃棄せずに新たな価値を生み出す「アップサイクル事業」として実施されました。
このプロジェクトは子どもたちや町の住民に喜ばれ、地域の絆を深めることを目指しています。南部町のプロジェクトは地域の魅力を広めるために行われたものであり、地域の人々や訪れる人々に向けて実施されました。

弘前工業高等学校 様
不要になったアクリルパーテーションをキーホルダーにして文化祭のカプセルトイ商品に
弘前工業高等学校では、新型コロナウイルス対策として使っていたアクリルパーティションを再利用し、キーホルダーに作り変えて文化祭のカプセルトイ商品として販売する取り組みを行いました。
このプロジェクトは情報技術科の3年生の樋口侑樹さんと小山内遊さんが企画しました。
プロジェクトの目的は、不要になったアクリルパーティションを廃棄せずに再利用し、学校の校章や校歌の一節などをデザインしたキーホルダーを作り、学校の文化祭でカプセルトイとして販売することで、学校のPRを行うことでした。子どもから大人まで楽しめるカプセルトイとして、地域の人々や訪れる人々に向けて実施されました。

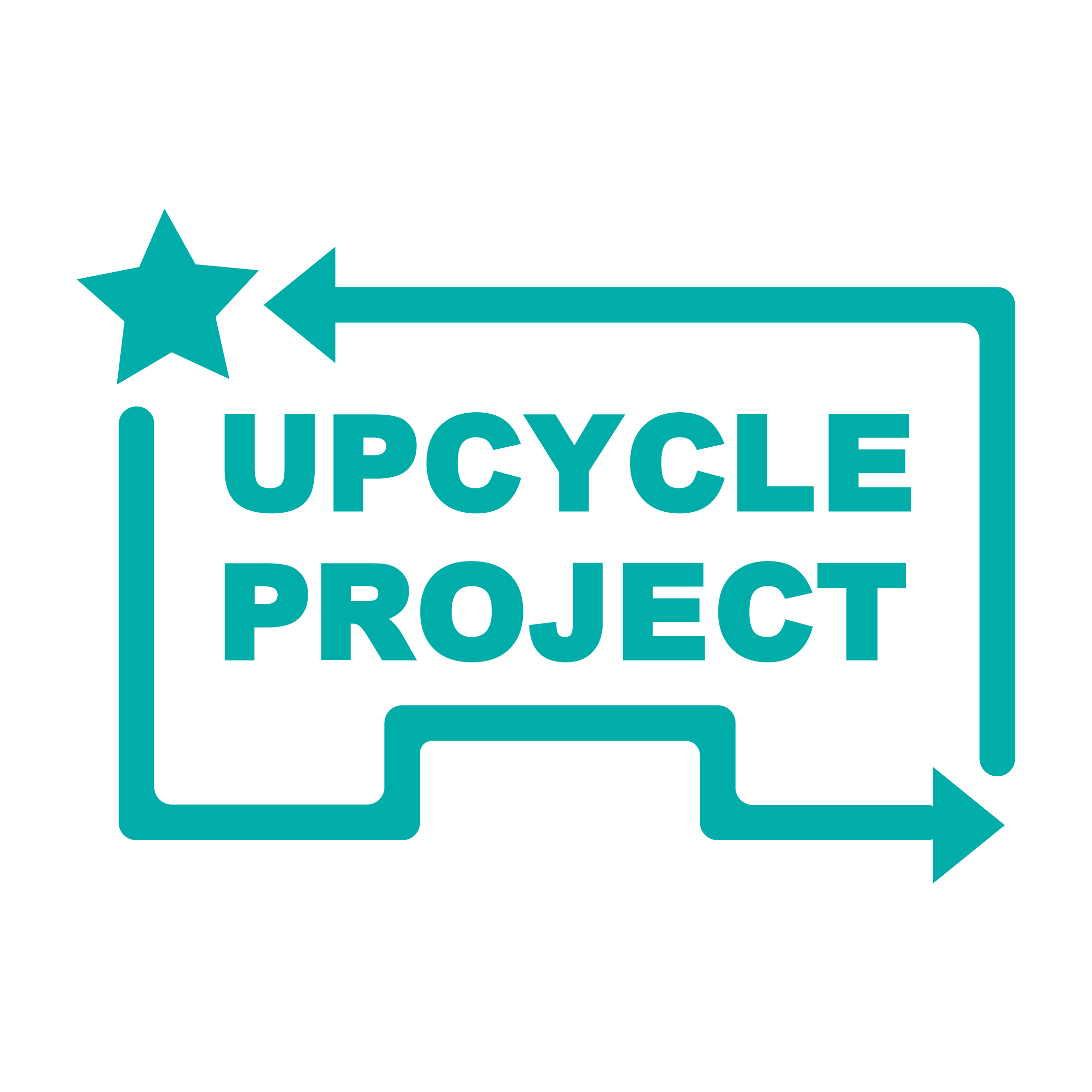
どちらのプロジェクトも、「今まで人々を遮ってきていたもの」⇒「人々をつなぐもの」への深化を意味し、アップサイクルの一例としてアサヒ印刷が提言しているものです。
ロゴマークにもその意味が込められており、本ロゴが佩された商品はアサヒ印刷でのアップサイクル商品です。